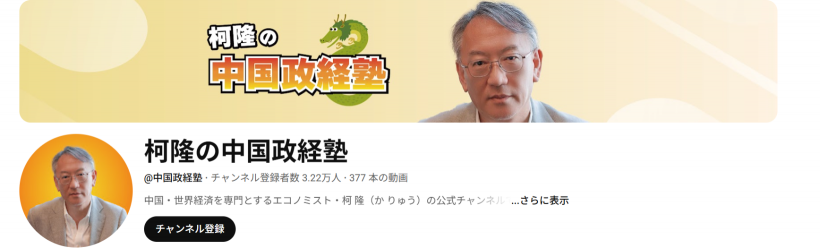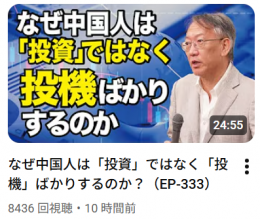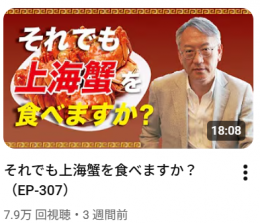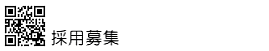いきてるぶんかのおていれ
季節は秋から冬に移り変わり「紅葉シーズン」が萩にも訪れ、既に寒冷地では熊は活発に活動していますが、樹々は成長を止めて休眠状態に移ります。5月後半から6月に「単葉法」「みどり摘み」で今年の成長点の新芽を総て摘み、成長を抑制して勢いの無くなった短い2番芽が複数発芽し枝先は丸く団子状態で風通し悪く、下枝や幹近くの枝に日光が当たらず͡此のママでは下枝や内側の枝は枯れて樹形が崩れて仕舞います。YouTubeでお勉強して「60の手習い」で失敗覚悟で新たな趣味に挑戦しています。植木職人は費用・施主の意向も有り素早くテキパキと毟りや剪定作業をしなければ次の年には仕事が無くなり、剪定作業シーズン中に沢山の現場をコナサナイトお飯の食い上げと成りますが趣味の園芸の延長の作業は自己責任・日にち薬の「のんびり」で来年春まで締切期限は充分デス。
庭の黒松は此処に座って30年前後ですが、幹径・枝振りからして最低でも200年~300年?の樹齢と思われます。YouTubeの黒松剪定の動画は若い庭師さんや趣味で代々庭木を弄って来た50代以上の中高年層が多く地域は関東から東海の比較的暖かい処の都市部で、空襲で焼けてしまったのか小振りな黒松の20~30年の庭木が多く地域の好みか樹形が萩辺りと異なります。出雲大社の隣りの庭木の育成畑の辺りはコノ樹形と同じような3mサイズが多く大根島の「由志園・ゆしえん」にも似た松が多く植わっていましたので地域性がある様です。
最近の隣りの大陸国家とかつての思想、文字・文化の共通点、肌の色、黒髪等の身体的特徴が似ていますが、似て非なるものとして付き合うのが得策と同国出身の経済学者がテレビやSNSで発信していて、「なるほど!」と納得して腑に落ちます。庭木を何十年何百年手入れして受け継いだり長期の基礎学問研究の文化が途切れてしまっているようです。