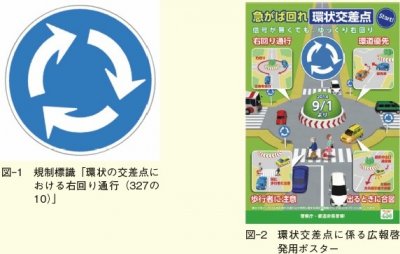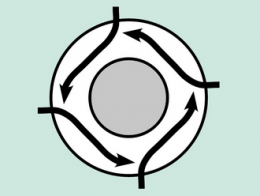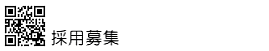春の「萩焼祭り」開幕
萩のゴールデンウィークの一番の催事は「萩焼祭り」ですが主催は萩商工会議所で観光協会・市の観光課が共催してます。毎年日付を決めて五月の一日から五日までが開催期間です。飛び石連休でウイークデイの開催で少し賑わいが足りませんが毎年コレを目的に来られる猛者もいらっしゃいます。お値段交渉も買い物の醍醐味です。

この幟旗が目印です

空模様が怪しく店仕舞いの支度を始めています


明倫学舎などの屋内のスペースや協賛店の幟の店へどうぞ

萩焼祭りの会場近くは、市営駐車場や明倫小学校など駐車スペースも充分過ぎるほどせいびされ、渋滞も無くユックリ・ゆったり楽しめます。